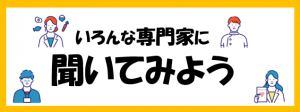
今年度、第3回の『いろんな専門家に聞いてみよう』は、理学療法士の濱田さんです。
~いっぱい転ぼう!~
私が医療現場にいた頃は、歩く練習や車いすに乗り移るときなど、
「患者さんを転ばせる」
「患者さんが落ちる」
ことはあってはならないことで、転ばないよう環境を整え、転びそうになったらすぐ介助ができるよう、細心の注意を払うことが日常でした。
すきっぷで子供たちと関わるようになり、当時おられた作業療法士さんは、運動遊び中に子どもたちが転んでも
「上手に転んだね」
「上手に落ちたね」
と声をかけておられました。
「上手に転ぶ?上手に落ちる?」ってどういうこと?と、私の頭は?でいっぱいでした。
子供たちにとって「転ぶこと、落ちること」はどんな意味があるのでしょう。

障害物があるとき、避けるもの(危険)が近づいてくるときには、
①見る・聞く:目や耳から情報を集める
②脳で判断:集めた情報をもとに「危険」を避けるための指示を全身に出す
③動く:脳からの命令通りに身体を動かし、タイミングを合わせて避ける
この①→③の流れには、周囲の状況に注意を向ける、飛んでくるものや近づいてくるものの位置関係を把握する(空間認知)、自分の身体がどうなっているかを把握し(ボディイメージ)、身体を保つよう(平衡感覚)、脳・脊髄・未梢神経・筋・関節が働くこと(運動器)が必要になります。これらがまだ発達段階にあれば、障害物に注意が向かなかったり、ドアや壁にぶつかったり、転んだ時に支える手が出なかったりということがみられます。
昨年のブログに登場したわが子も、幼いころ、私のほうを向いて笑顔で走っていました。
それはそれで可愛いのですが、当然、電柱にぶつかったり、段差に気付かず転んだり、雑巾がけでつんのめって顔面を強打したり・・・小さな怪我の多い子でした。
そうなのです!
大きな怪我につながらないよう、転ぶこともまた経験なのです。
安全な環境下での遊びを通して、転ぶ、転がるなど様々な動きや刺激を経験し、転ばないための①→③の流れを作っていく過程が大切なのだと思います。
つまり「上手に転んだね」「上手に落ちたね」は、この流れを育てていく誉め言葉でした。
また、大人はつい「あ~また転んで」と言ってしまいたくなるのですが、転ぶことへのnegative な感情を生むことなく、「転ぶことも大切」と私たちにも再確認させてくれる言葉だなと思います。
子供たちと転がったり、跳んだりしながら、鈍くなってきた私の感覚は大丈夫かしら?
と思う今日この頃です。
一緒にゴロゴロ転がってみたり、危ないと思ってもぎりぎりまでは手を出さず、子供たちが上手に転ぶ姿を一緒に見守ってくださるとうれしいです。
